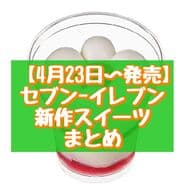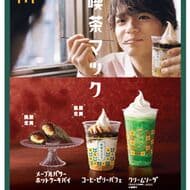さて。日光東照宮へ年始のお参りに訪れた帰り道、ふといつもは通らない西参道を歩いてみたところ、ちょっとした人だかりを発見。近づいてみると、あま~い香りの漂うたい焼き屋さんでした。店の名は亀六(きろく)、商品名は「昔のたい焼」。

“昔の”たい焼きって、どういうことなのでしょう。ピンとこなかったため、焼き上がりを待ちながら、店主らしきお父さんに聞いてみました。
生地の材料は、粉と水、味付けのための少しの塩、そして砂糖だけとシンプル。一般的なたい焼きは「ホットケーキみたいな生地で作られている」ため膨らみやすいのですが、お父さんのたい焼きには卵やベーキングパウダーなどが入っていないため、焼き上がるまでに時間がかかるのだそうです。
年季の入った焼き型を見てみると、1つで6個分の型があるにも関わらず、真ん中の4つしか使われていません。火力の都合で端まで熱が回らないそうです。「今のやつは端でもきれいに焼けるんやけどね」とお父さん。たい焼きをひっくり返したりしながら、片手で次の生地を混ぜています。
手間がかかっても、“昔ながら”の製法で作られているから「昔のたい焼」だったのです。

羽はもちろんパリパリ。わざと作られたものではないため厚さにもばらつきがありますが、だからこそ特別に感じてしまいます。ほんのり塩気もあって、ギョウザの羽をパリパリ食べているみたい。
本体部分の皮は、ふっくらとはしていないけれど、たっぷり入った餡(あん)と見事に一体化。外側はパリッと、中はしっとりと仕上がっています。塩気のおかげで、ぎゅっと味が引きしまっているのも印象的。素朴な味わいにほっと心が安らぎました。きっとお父さんの人柄もあるのでしょう。お父さん、ありがとう。

お店があるのは、二荒山神社の大鳥居前から西参道を少し下ったところ。トラックとのぼりが目印です。真夏の営業日には熱中症で倒れてしまったこともあるという、お父さん。また来年もこのたい焼きを食べられることを願ってやみません。